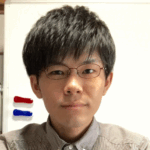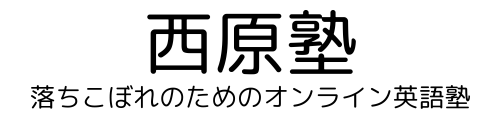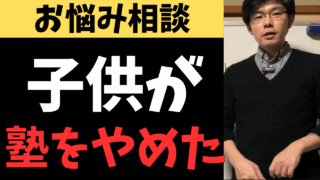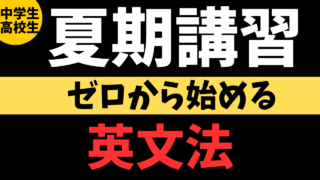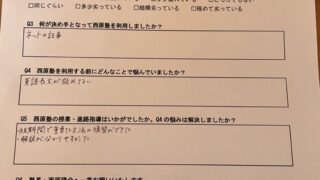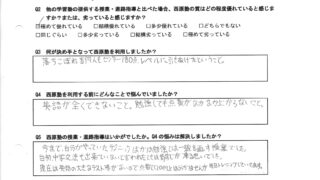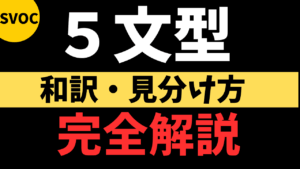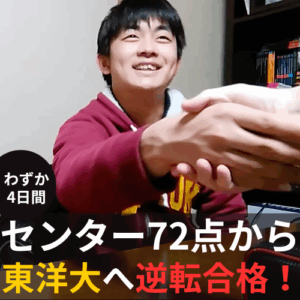勉強しない子どもに親がするべき2つのこと・してはダメな3つのこと
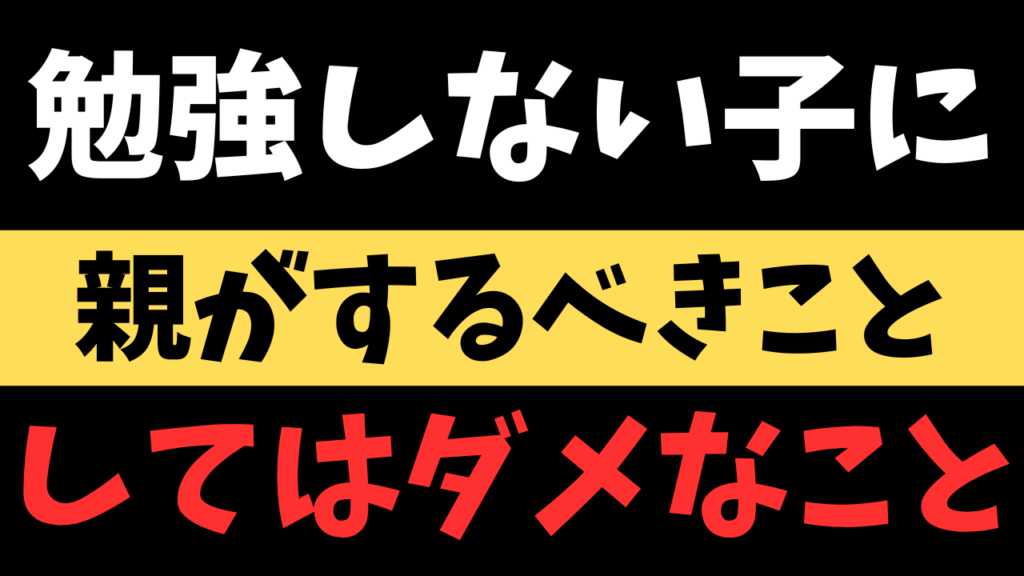
みなさんこんにちは。
西原塾の西原陽介です。
今回は一番多いお問い合わせでいただく相談内容で一番多い「勉強にやる気を出さない子にどう接すればよいか」についてお話ししたいと思います。
この「子どものやる気」問題。
実はこれ、お父さん・お母さんが適切に対応しないと家庭が崩壊する危険性すらあるとても重大な問題です。
お父さんとお母さんでお子さんへの対応のしかたで対立してケンカになってしまったご家庭…
お子さんのことを思ってのアドバイスを拒絶されて親子関係が悪くなってしまったご家庭…
など、この「子どものやる気」問題の対処を誤ったがために関係がギクシャクしてしまったご家庭を数多く見てきました。
今回は子どもが勉強にやる気のない時、何をするべきなのか、そして何をしてはいけないのかをお教えします。
勉強しない子どもに親がするべきこと
子どもが勉強に対してやる気を出さない時、とても焦りますよね。
「この子は将来なにをしたいのだろう・・・」
「この子はなにをするつもりなのだろう・・・」
と悩んでしまうと思います。
我が子を想うあまり、「勉強したほうが将来潰しが効くから」と勉強をさせようとしてしまいがちです。
ですがこれは大体お子さんには拒絶されてしまいます。
せっかくアドバイスしたのに断られればお父さん・お母さんも大人とは言え、当然カチンときます。
そうしてケンカとなり、お互いに意地になってそのまま硬直状態におちいってしまうご家庭をたくさん見てきました。
こうなってしまうとお互いに話し合う機会を失ってしまい、解決は難しくなります。
でも、良かれと思って言った一言が気づかぬうちにお子さんを追い詰めてしまう可能性があるのです。
あなたも自分のお子さんを追い詰めたいわけではありませんよね。
そんな不幸なことにならないよう、まずはお子さんが勉強にやる気のない時に、親がするべきことをお話しします。
子どもが何を望んでいるかを確認する
まずはあなたのお子さんが「何を望んでいるのか」をしっかり聞きましょう。
これはあなたのお子さん自身の意志とも言いかえられます。
まだ「〜したほうがよい」とアドバイスしてはいけません。
子どもからすれば「僕/私の意見なんて聞いてくれない」という印象を持ち、せっかくのアドバイスが「親の意見の押しつけ」になってしまいます。
また、お子さんの考えがどんなにくだらないことだとしても絶対に否定してはいけません。
これをやってしまうと一発でアウト、確実に親子関係がこじれます。
重要なのは、お子さんのしたいこととしたくないことという、お子さん自身の意志を尊重することです。
そしてあなたがそれを見守ることです。
今まで多くのご家庭を見てきた結果、勉強しない子の「望み」は大きく分けて、
- 勉強をがんばりたい・成績を上げたいが、何から始めればよいか分からない
- 勉強以外のことを実はやりたい
- 得にやりたいことはないが、少なくとも勉強はしたくない
という3パターンに落ち着きます。
それぞれのケースに対して、あなたがどう対応するべきかをお話しします。
勉強をがんばりたい場合
あなたのお子さんの理解力や論理的思考力に合わせて1から教えてくれる塾・予備校・学校・家庭教師を探しましょう。
そして信頼できる人を見つけたら、お子さんを預けて後はその人の指示に従ってください。
このケースの場合、お子さんはやる気がないのではありません。
やる気はあるけれども、何をどう勉強すれば良いかわからないから行動できないだけなのです。
その行動できない状況だけを見て勝手にやる気が無いと判断してしまっているのです。
このケースの子が陥る最悪のパターンとして私が実際に見たことがあるのは、
- 勉強したいが何から始めればよいのか分からない。
- でも勉強しないといけないことは分かっているから、とりあえず何も考えなくても始められる暗記から取りかかる。
- しかし暗記作業は単純でつまらないうえに、すぐに成績に反映されるわけではないので達成感を感じにくい。
- 気がつくと勉強を続けることが目標になっていく。
- 気合で勉強を続けるが、我慢の限界が来て勉強習慣が途切れてしまう。
- 「毎日勉強できないなんて自分は不真面目だ」
「まだまだ追い込みが足らない」と自分を責める。 - また勉強を再開するも、そのうちまた習慣が途切れてしまう。
- また自分を責める。
- これを繰り返していくうちに自分に自信がなくなり、「僕/私はダメだから」と自分の能力を否定することで勉強できない理由を作り出す。
- 何をするにも「どうせ自分はバカだから」と自己否定して、勉強そのものを拒絶する。
- でも勉強をしていない罪悪感は持っていて、さらに自分の行動の愚かさも分かっているので、同じ境遇の仲間を求め始める。
- 成績の低い人同士で集まったり、勉強している人・これからがんばろうとしている人たちを「そんなことしても無駄だ」と小馬鹿にし始める。
という地獄の展開がありました。
このパターンの子は意外と多く存在します。
こうなってしまわないためには、やる気があり「がんばってみよう!」という気持ちがあるうちに正しい勉強法を知ることが重要です。
そして、少しずつでも「なんかできるようになってきた気がする!」と「小さな成功体験」を実感させてあげることです。
勉強を始めて半年程度は模試の結果が悪くても構いません。
テストの点数や、偏差値などの数字ではなく、
「前に比べて英文が読めるようになった」
「問題の解き方がすぐ思い出せるようになった」
などといった、小さな成功体験が子どもたちに自信を持たせ、「このまま行けばそのうち…いい成績とれるかも!」と期待を持たせます。
その期待は楽観的ですが、その楽観的な期待こそが勉強に対する前向きな姿勢を生み、やる気に繋がります。
独学でがんばらせるのは×
よくある失敗として、正しい勉強法を参考書やインターネットで調べて、後は子ども本人にがんばらせるお父さん・お母さんがいます。
これは絶対にやめましょう。
本人に任せるのではなく、必ず塾・予備校・学校・家庭教師の先生を探して、後はその先生に任せてください。
独学ではなく、先生に任せる2つの理由
理由は2つあります。
まず1つ目の理由は、優秀な先生はあなたのお子さんに合った勉強法や指導法を判断できるので、良い勉強法を確実に手に入れることができるからです。
参考書やインターネット上の無数の情報から正しい勉強法を見つけ出すのは至難の業です。
正しい勉強法を探しているうちにどれが良いのか分からなくなってしまい、だんだん嫌になってしまいます。
これでは勉強を成功させるための方法を探すことに疲れて、勉強自体を始められないという本末転倒に終わってしまいます。
勉強法探しだけでなく、先生探しもこだわりだすと止まりません。
「あ、この先生良いかも」って思ったら一度話を聞き、良い印象が変わらないのならすぐその先生に任せましょう。
2つ目の理由は、先生との二人三脚の方が毎日の勉強を続けられる確率が高いからです。
勉強はどんなに良い方法であっても続けることができて始めて効果を生み出します。
大半の人間はひとりでなにかを毎日続けることは苦手です。
これは子どもも大人も同じです。
大人だってダイエットや英語学習を毎日欠かさず続けられる人なんてごく一部ですよね。
それは、「何を」「何のために」「どのくらい」「どのように」勉強すれば良いのかを毎日自分で考えながら続けるということはとても体力のいる、大変なことだからです。
だからこそ、この部分を誰かに任せて、自分は与えられたものを毎日こなすことだけに集中すれば続けられます。
大人で言えばライザップが分かりやすい良い例ですね。
ライザップでは毎日どんな運動をして、何を食べればよいのかパーソナルトレーナーが指示をしてくれて、利用者はその指示に従うだけで理想のボディを手に入れています。
勉強でも同じです。毎日何を勉強すればよいのか、どれくらい勉強すればよいのか指示をしてくれる先生といっしょなら毎日続けることができます。
何を勉強するべきか教えてもらうことは悪ではない
中には「何を勉強するべきか考えることもまた勉強」という哲学的な意見を持つお父さん・お母さんもいます(特にお父さん)。
この考えは正しいですが、実践する時期を間違えています。
これは自分がどうすれば物事を進められて、身につけれれるかを知っている人が実践するべきことです。
言い換えれば、一度何かを得意と言えるレベルにまで身につけたことがある人です。
子どもが自転車を乗れるようにする時に「どう乗るか自分で考えてみろ」という指示はしないですよね。
旧日本軍の海軍大将、山本五十六氏の言葉に、
「やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ」
というものがあります。
最初は何をどう勉強するのか指示を出してくれる先生に任せることが一番の近道です。
まじめな子が陥りがちな罠
まじめな子に多い失敗として、1日10時間勉強や参考書20ページなどの大量の勉強をいきなり自分に課してしまうケースが見られます。
あえて大量の勉強を自分に課すことで、今まで勉強してこなかったことに対する罪悪感や、今成績が低いことに対する自分への嫌悪感から逃れようとしているのです。
そしてこれを気合で続けようと、乗り越えようとし、できなければ「やる気が足りない」「追い込みが足りない」「自分は情けない」などと精神論で乗り切ろうとしてしまいます。
勉強は気合で続けるものではありません。
大半の子は上の地獄のケースのように勉強を続けられない自分に絶望して、途中で燃え尽きてしまいます。
一度燃え尽きてしまうとやる気を取り戻すには時間がかかります。
優れた先生ならば、今のお子さんが続けられる勉強量・勉強時間で可能な限り成績を上げるプランを考えてくれます。
この点からも、独学ではなく、信頼できる先生にお子さんを任せることを強く勧めます。
先生探しの注意点
先生は学校・塾・予備校・家庭教師なんでも構いませんが、『(難しい)問題の解き方』ではなく、『各科目の勉強法』を教えてくれる先生を探してください。
多くの学校・塾・予備校・家庭教師は問題の解き方はわかりやすく教えてくれますが、成績の上げ方は教えてくれません。
また、基本的に中学・高校・学習塾・予備校では最初から勉強法や勉強習慣が身についている優秀な子や、思考力が高い、暗記力が高いなどの好成績に届く可能性のある子にしか手厚い指導はしません。
こういう先生にお子さんを任せてしまうと、毎日何を勉強すればよいのか・どう勉強すればよいのか・そして毎日の勉強習慣はどう身につければよいのかをお子さん自身で考えなくてはならず、意味がありません。
特に中学・高校の先生でここまで手厚く指導してくれる(指導できる)先生はほぼいないので注意してください。
勉強以外のことを実はやりたい場合
あなたのお子さんが望むことを思う存分にさせましょう。
勉強させないで構いません。
むしろ勉強をムリヤリさせるのだけは絶対にやめてください。
これまた私が過去に見た最悪のパターンとしては、
- 勉強したくない。他にやりたいことがある。
- でも親・学校が勉強しろと言うし、常識的にも勉強しない訳にはいかない。友達も勉強しているし。
- とりあえず何も考えなくても始められる暗記から取りかかる。
- しかし暗記作業は単純でつまらないうえに、すぐに成績に反映されるわけではないので達成感を感じにくい。
- さらには本当は勉強に興味がなく、他にやりたいことがあるので当然勉強に身が入らない。
- 気がつくと勉強を続けることが目標になっていく。
- 気合で勉強を続けるも、我慢の限界が来て勉強習慣が途切れてしまう。
- 「毎日勉強できないなんて不真面目だ」
「まだまだ追い込みが足らない」と周りに責められる。 - また勉強を再開するも、そのうちまた習慣が途切れてしまう。
- また親や学校から責められる。
- これを繰り返していくうちに「嫌なこと(勉強)を我慢してやっているのに、なぜ文句を言われなくちゃいけないんだ」と不満を持つようになる。
- または「勉強を続けられないなんて自分はダメなのか」と自信を失うようになる。
- 親や学校に反対して自分のしたいことに挑戦することもできず、元々興味のない勉強に集中することもできず八方塞がりでもがき苦しむ。
という悲しい展開がありました。
ちなみに私はかつてこの状態で、本心では大学入試にも学歴にも興味がないのにもかかわらず、「早慶上智に入らないとマズイ」という固定観念にとらわれて2浪までしました。しかも結果は失敗でした。
人は子ども・大人にかかわらず興味のないものには集中できません。
興味のないもの・嫌いなものを無理矢理やらされているわけですから当然です。
でもあなたのお子さんは興味のあるなしに関係なく、成績が低ければ親や学校の先生や友達から色々言われるわけです。
こんな理不尽なことはありません。
学校を辞めるというのはそうそう選べる選択肢ではないのでしかたないにせよ、せめて学校以外の時間は興味のあるものに熱中させてあげてください。
今すぐお子さんを興味のないものに対する努力から開放してあげてください。
「潰しが効く」という理由で興味のない勉強をやらせていても、その先には明るい未来などありません。
勉強させないという選択はとても不安だと思いますが、どの道好きでもないものを努力しても良い結果は生まれません。
特にやりたいことはないが、少なくとも勉強はしたくない場合
この場合も勉強させないで構いません。
好きなことが見つかるまで放っておきましょう。
たとえ勉強の代わりになることがなくても、勉強をムリヤリさせるのだけは絶対にやめてください。
上にも書きましたが、人は子ども・大人に関係なく興味のないものには集中できません。
たとえ他にやりたいことがないとしても、勉強をしたくないという気持ちがある以上、無理矢理やったところで長続きしませんし当然成績も上がりません。
それはお子さん本人が悪いわけではなく、人ってそういうものなのです。
時間と労力のムダかつ、お子さんにストレスを与えるだけなのでやめましょう。
好きなこと・やりたいことというのは自然と現れます。
必ず現れます。
やりたいことを見つけたら、自然とその方向へ努力するようになり、自然と道が開けていきます。
私が大学を中退してから学習塾を開くまでもそうでした。
やりたいことが見つかるまでは時間がかかるかもしれませんが、その時まで見守ってあげてください。
お子さんの人生について不安なのはあなただけではありません。
お子さん本人だってやりたいことが無い自分に対して不安なのです。
責めたりせず、静かに見守ってあげてください。
勉強は潰しが効くは通用しない
特にやりたいことがないのなら勉強だけでもやっておけば…とあなたは思っているかもしれません。
気持ちは分かりますが、残念ながらそれは不可能です。
中学生・高校生の多くは、「未来から逆算して今の行動を決める」ということはできないからです。
なぜなら、そこには未来から逆算して決めた今するべき行動が、今の自分にできることなのか、続けられることなのかという視点が欠けているからです。
とりあえず勉強しておいたほうがあとで潰しが効くことくらい、あなたのお子さんは分かっています。
たとえお子さんが中学生・高校生であってもこのことはみんな理解しています。
でもこの考え方には「興味のないもの(=勉強)を毎日できるのか」という視点が欠けています。
だから英単語帳5ページずつなど、毎日続けられるであろう勉強量を毎日課したとしても大抵続かないのです。
これはあなたのお子さんが不真面目だからではなく、興味が無いから続けられないなのです。
何度も言いますが、人は興味のないものには集中できません。
人間とはそんなものです。
お子さんの意思を尊重する
あなたのお子さんが何を望んでいるのかによってあなたが取るべき対応は分かれています。
ざっとまとめると、お子さんが
- 勉強をしたいのなら、
→ 信頼できる先生に預ける。 - 他のことがしたいのなら、
→ 無理に勉強させず、好きなことをさせる。 - 特にやりたいことがないのなら、
→ 無理に勉強させず、自然とやりたいことが現れるのを待つ。
このようになります。
2と3の勉強をさせないというのは、なかなか受け入れにくい考えだと思います。
なぜ、強制的に勉強させないのか?
好きなものは自然と上達するという意味のことわざに「好きこそものの上手なれ」という言葉があります。
私は今後、この「好きこそものの上手なれ」で得た知識や技術以外は価値がなくなると思っています。
嫌いなものに対して努力したところで並の知識・技術しか得られません。
イヤイヤやって手に入れられるものなどたかが知れています。
でも努力に伴う苦痛は多大です。
多大な苦痛を味わって並の知識・技術を手に入れても、並の知識・技術など誰もが持っています。
結局はみんなといっしょ。それを職にして生きていけるわけでもありません。
イヤイヤ勉強した私の体験談
具体的な例を挙げると、イヤイヤ受験勉強をしていた私がたどり着いたのは平均的な学力でした。
平均的だと学力自体ではほかの人と差をつけられません。
あの頃は自分が今していることに価値を感じられませんでした。
そんな自分に対する焦りから、将来自分がどうなるのか、どうなりたいかさえも考える余裕など全くありませんでした。
ただ勉強を続けられないことに対する罪悪感と、そんな自分に対する嫌悪感、そしてだんだんと迫ってくる試験日への焦りで思考停止に陥っていました。
効果があるのか分からない暗記術なるものに手を出そうと真剣に考えていた程です。
でも2浪目の秋に勉強を完全にやめて、ひとりで自分自身について向き合って考え、
「学歴は欲しいが、このまま苦痛な受験勉強を耐えてまでは欲しくない。」
という自分の本心に気が付きました。
そして方向転換して、まずは「英語を読めるようになりたい」という望みを叶えるために海外の大学に入りました。
その大学は日本・海外ともに無名で、早慶上智という学歴にこだわっていたついこないだまでの私には到底考えられない選択肢でした。
大学では私の好きな議論・作文中心の授業が行われていて毎日楽しく勉強できました。
2浪までしてもセンター試験で100点を切っていた英語力がわずか3ヶ月で180点を取るまでに成長し、最初はチンプンカンプンだった教授の英語が聞き取れるようにもなりました。
大学入試という自分の好みに合わない制度にプレッシャーをかけられながら勉強したのではなく、議論・作文中心という自分の好きな方法で勉強できたからここまで短期間に能力が向上したのです。そしてその体験をひとりでも多くの子に伝えるべく学習塾を開きたいと思うようになりました。
今の私が成功のモデルケースと言えるかは微妙ですが、少なくとも浪人時代には全く感じていなかった未来への希望と毎日の喜びは得られています。
そして好きなことがある程度上達した今となっては、意味を感じられなかった浪人時代のことを人にお話する機会に恵まれるようになりました。
私が開いている西原塾に来る人の大半が、この体験を書いた私の自己紹介を読んで、「一度失敗している先生ならうちの子を任せられる」と考えてくださった方です。
好きなことをして、それをある程度上達させられた今だからこそ、かつての苦労・失敗を武器にできています。
私はあなたのお子さんに私と同じ失敗をしてほしくありません。
私は生まれつき自信過剰なので、2浪までしても「俺なら大丈夫。最後はうまくいく。」と根拠のない自信を持っていたので、常に前向きに自分の道を探し続けられましたが、多くの子はそうなりません。
2浪まで行けば自分への絶望感と周りからのプレッシャーに押しつぶされてしまう子がほとんどでしょう。
過程はさまざまですが、本当に多くの子が親や学校に反対して自分のしたいことに挑戦することもできず、元々興味のない勉強に集中することもできず、八方塞がりでもがき苦しんでいます。
嫌なことをムリヤリさせて小さな失敗経験を重ねて自分に自信を失ってしまう前に、好きなことをやらせてあげてください。
そしてその道で小さな成功体験を重ね、自分自身に自信を持たせてあげてください。
勉強しない子どもに親がしてはダメなこと
ここまでお子さんに対してあなたがするべきことを挙げました。
次はお子さんと接する時に、お父さん・お母さんが特にやりがちな「してはダメなこと」についてお話しします。
むりやり勉強させる
上で散々お話ししてきましたが、いくら勉強に対してやる気がないからと言ってむりやり勉強させるのだけは絶対にしないでください。
やる気というのは出すものではなく、自然と出てくるものです。
趣味に取り組んでいる時の自分を想像するとよくわかると思います。
「よし、集中しよう!」と言って集中する人などいません。
何かに取り組んでいるうちに自然と集中力が上がっていくはずです。
勉強も同じです。
あなたのお子さんが勉強を本当に求めているのであれば、自然と集中していくはずです。
これは「勉強を趣味のように楽しめれば」という意味だけではありません。
「高校受験・大学受験・大学卒業後に何か目標があり、その目標のために勉強する必要があることを認識していれば」という意味でもあります。
つまり、お子さんが勉強に集中しない、やる気を出さないということは、
- 勉強が好きではない。
- 自分の目標と勉強が(今のところは)関係ない。
ということです。
こんな状態なら勉強にやる気が出なくて当然ですし、むりやり勉強させたところで成績が上がる訳がないというのも理解できると思います。
あなたも興味がなく、しかも自分の生活に無関係なものに対してがんばれと言われても困りますよね。
兄姉と比べる
これはやる気を出さないお子さんに、ある程度優秀なお兄さん・お姉さんがいるご家庭でよくやってしまう過ちです。
たとえ兄弟・姉妹であっても、それぞれ別々の人間です。
- 何が好きなのか
- 何が嫌いなのか
- 将来何をしたいのか
- 将来について決まっているのか
- どれくらいの理解力を持っているのか
- どれくらいの暗記力を持っているのか
これらは兄弟・姉妹で同じである必要は全くないわけです。
ならば、
「この時期はお兄ちゃん偏差値xxくらい取ってたよ」
「お姉ちゃんxx大学入ったんだから、あなたもがんばらなきゃ」
「お兄ちゃんは高校生の時に将来の目標決めてたけど、あなたはどうなの?」
というような言葉はいかにお子さんの自尊心を傷つけているかわかると思います。
兄弟・姉妹であっても別々の人間ですから、好みに違いがあるのは当然、将来の目標が決まる時期が違って当然、得意不得意が違うのも当然、能力に差があるのも当然です。
子どもを信じましょう
兄姉と比べてはいけない理由を書いてきましたが、恐らくこれを読んでいるあなたはこんなことすでに分かっていると思います。
兄弟・姉妹であっても比べてはいけない。
そんなことは分かっている。
でもつい「お兄ちゃんは〜」「お姉ちゃんは〜」と言ってしまう。
不安なんですよね。
弟さん・妹さんのことが。
弟さん・妹さんがかわいくて、立派に成長してほしくて、だからお兄さん・お姉さんと比べてしまうんですよね。
でも少し考えてみてください。
優秀な兄・姉と比べられる子のことを。
あなたのお子さんは、
「お父さん・お母さんは僕/私ではなくお兄ちゃん・お姉ちゃんの方がかわいいんだ。だから自分にも同じようになって欲しいんだ。」
「僕/私はお兄ちゃん・お姉ちゃんのコピーじゃない」
「もっと僕/私のことを見て、考えて相談に乗って欲しい」
と思っています。
ちなみに上の3つは私の弟が、母に対して実際に言った言葉です。
兄弟・姉妹であってもそれぞれ別々の人間です。
ひとりがうまく行っても、他の子がうまくいくとは限りません。
お子さんが2人なら2人分、3人なら3人分の多様な人生があるわけです。
お子さんたちを産んだお父さん・お母さんには彼らの多様な人生を受け入れてあげましょう。
すでにうまく行っている上の子と比べてプレッシャーを与えるのではなく、「私(達)の子なら最後にはうまくやるさ!」と成功を信じて待ってあげましょう。
お子さんを信じる上で根拠など必要ありません。
この先うまくいく予兆がなくても、希望が見えていなくても、ただお子さんを信じて待てばよいのです。
あなたのお子さんはあなたが思っている以上に自分の人生について考え、悩み、そして努力しています。
必ず最後にはあなたの信頼に応えてくれます。
「〜したほうがよい」とアドバイスする
上で書きましたが、お子さん(特に中学生・高校生)に対するあなたからのアドバイスは、本人にはアドバイスではなく「意見の押しつけ」に聞こえています。
彼らは自分の人生についてアドバイスが欲しいのではありません。
自分の考えを応援してほしいのです。
だからあなたが「〜したほうがよい」と経験論からアドバイスをしたとしても、そしてそれが正しいアドバイスだとしても、お子さんには受け入れられません。
時にはあえて痛い目にあわせることも必要
もちろんお子さんの言うことは世間を知らない甘い考えかもしれません。
大人であり、世間の酸いも甘いも知っているあなたからすれば馬鹿げていると感じるでしょう。
でもそれをそのままお子さんに話してもムダです。
人間は何事も自分自身で経験してみないと知識として受け入れることはできません。
例えば、あなたのお子さんのやりたい事が声優になることだとして、「声優として食べていけるのはひと握りの人だけ」とアドバイスしたとします。
この考えは正しいです。しかし、「自分はそのひと握りになれるかもしれないから挑戦したい」とお子さんは思っているのです。
だからこのアドバイスはムダになるわけです。
どんなに正しくて理論的なアドバイスでも、本人が実践して、実感できて初めて知識として受け入れることができるのです。
お子さんの考えが失敗するであろう甘い考えだとしても一度挑戦させてあげましょう。
そして成功したら儲けもの、失敗したらそこで初めて「僕/私の考えは甘かったんだな。」とお子さんはひとつ学ぶわけです。
まとめ
親がするべきこと
子どもが勉強したいとき
やる気がないのではなく、何から始めればよいのか分からないだけです。
難しい問題の解き方ではなく、各科目の勉強法を知っている良い先生に預けましょう。
親がするべきこと
子どもが勉強以外のことをしたいとき
むりやり勉強させず、好きなことを自由にやらせてあげましょう。
強制的に勉強させても、誰も得しない結末が待っています。
親がするべきこと
子どもがやりたいことを持っていないとき
むりやり勉強させず、好きなこと・やりたいことが出てくるまで自由に過ごさせてあげましょう。
好きなこと・やりたいことがなくて不安なのはお子さんも同じです。プレッシャーを与えるのではなく、好きなことが見つかるまで優しく見守ってあげることが大切です。
親がしてはダメなこと
むりやり勉強させる
自然と勉強しないということは、お子さんにとって勉強は好きでなく、かつ自分の目標と関係ないものということです。
だから強制的に勉強させても成績はあがりません。
親がしてはダメなこと
兄・姉と比べる
兄弟・姉妹といえども別々の人間なのだから、能力や好みが違って当然です。
優秀な兄・姉と安易に比べることは、下の子の自尊心を傷つける最低の行為になります。
親がしてはダメなこと
「〜したほうがよい」とアドバイスする
「〜したほうがよい」とアドバイスする人間は自分で試してみて、身をもって実感したことでないと知識として受け入れることができません。
あえて失敗させることも人生における学習となり、お子さんの成長を促します。
人が生きていくうえで必ずしも勉強が大切とは限りません。
スポーツ選手、お笑い芸人、芸術家など、学校の勉強とは関係のない能力が必要とされる仕事もあります。
また、今はネット社会全盛の21世紀です。
今までの常識では考えられないような新しい仕事が生み出されています。
そして同時に、今まで安泰とされていた仕事が消えていっています。
これまで正しいとされてきた、良い高校・大学→良い会社へ就職という流れは正解とは言い切れません。
良い高校・大学に入ればそれだけで良い会社へ就職できるわけではありませんし、仮に良い会社へ入ったとしても、これからは解雇・倒産が普通にあり得るの世の中になっていきます。
大企業に入れたとしても過酷な環境で心身を壊してしまうかもしれません。
勉強というのはよほど優秀でないと世の中を生き抜く武器にはなりません。
これからの時代あなたのお子さんが持つべきなのはそこそこの学力などではなく、自分の趣味・特技を仕事にまで昇華させる能力です。
そのためにはお子さんをむやみに勉強に縛り付けるのではなく、自由にさせてあげること、そして趣味・特技を仕事レベルにまで磨きあげる時間と心理的余裕を与えてあげることです。
私が開いている西原塾には数多くのお子さんが入塾希望で来ます。
ですがその大半はお父さん・お母さんがお子さんを心配するあまり、お子さんの意志を聞かずにとりあえず塾にいれようとしているケースがほとんどです。
勉強したいと思っているかどうかは面談をすればすぐにわかります。
「この子は勉強したいと思っていないな」と感じたお子さんは入塾をお断りし、ご家族でお子さんのしたいことについて話し合いをするように伝えています。
この文章をお読みのあなたも、ぜひお子さんと「何をしたいのか」「何をしたくないのか」について、じっくり話し合ってみてください。
投稿者プロフィール